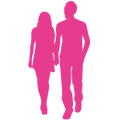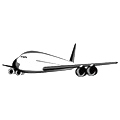ケンは、例によってトーマスクックのヨーロッパ版のタイムテーブルを広げ、ジュネーブからマドリッドまでの接続を調べた。彼は、旅費を浮かすために夜は極力夜行列車(TEE)の中で寝て、翌朝、目的地へ着くようなスケジュールをいつも組むようにしていた。
ジュネーブから、スペインの首都マドリッドまでは約1,500㎞の行程である。
TEEをうまく乗り継いでも、丸一日近くはかかってしまう。
しかし、貧乏旅行をしているケンにとっては、時間よりも、宿代を節約できることの方が有り難かった。
ジュネーブを午前11時27分に出発したTEEは、国境の駅に到着し、ここで、列車のレールが広軌から狭軌に変わるため、列車の車輪が狭軌用に交換される。
その作業の様子をケンは、列車の窓から何気なく見ていた。
「パスポール・ポルファボール」
スペイン人の入国管理官が数人、列車に乗り込んできて、簡単な検閲を行った。実に儀礼的な入国手続きである。
ケンを乗せた列車は2時間近く遅れ、バルセロナへ到着した。おかげで、彼が乗る予定にしていた乗り継ぎの列車はとっくに出てしまっていた。
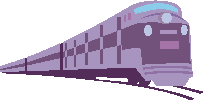
ホームへ降りると背の低い中年の車掌が、何やらスペイン語でがなり立てながら、近付いて来た。
周囲の乗客に聞いてみると、乗り継ぎの列車が待機しているので至急乗るようにとのことだった。
ケンは、他の乗客と共に慌てて、向かいのホームに停車しているTEEに乗り込んだ。中年の車掌は、早口で何やらしきりにしゃべりながら、てきぱきと乗客を4人用の寝台コンパートメントへ振り分けていった。
ケンは、2人のアメリカ人の青年とオーストラリアから来たという牧師と一緒に狭い2段ベッドが2つ並んだコンパートメントへ押し込まれた。
コンパートメントの中は、エアコンもなく、4人の男たちの体臭と真夏の夜の熱気の名残でうだるほどの蒸し暑さだった。
ケンが、上段のベッドへ荷物を解いて寝る準備をしている所へ、先程の貧相な車掌が入って来た。
何やらしきりにスペイン語で話していたが、要約するとこの列車は寝台車なので、ユーレイルパスは使えないという、差額として3,000ペセタを払わなければならないということらしかった。
ケンは、以前友達からスペインに行けば1日、1,000ペセタで充分生活できると聞いていたので、この3,000ペセタという額に抵抗を感じた。それによく考えてみると列車が遅れて、寝台車に乗るはめになったのは、自分の責任ではない。
ケンは、そのようなことを根拠に、この車掌に英語でまくしたてたが、彼には全く通じないらしく、ただスペイン語で、
「3,000ペセタ……」
と言いはるばかりであった。
ケンは、この頑固な車掌に、2段ベッドの上から計算機を使ってペセタの換算レートを示しながら一生懸命に自分の正当性を主張したが、やはり言葉の壁は厚く、彼には一向に通じなかった。
そこへ、二人の会話が列車が発車した後も延々と続いているので、隣のコンパートメントから、ケンと同じ年頃のブロンドのスーザンというアメリカ人女性が現れて、流暢なスペイン語でケンと車掌の中に入って割り、通訳を始めた。
それでもケンとこの車掌はその後1時間近くも、スーザンを挟んでお互いの意見を主張して一歩も譲ろうとしなかった。
「オーケイ、二人とも、ちょっと待ってよ。私はケンの言うことも分かるわ。でも、この車掌さんの言うことだって一理あるわよ。どっちにしろ、あなたが幾らか払わなきゃならないことは確かなんだから。」
とうとうしびれを切らしたスーザンは、もうこれ以上は我慢できないとばかりに、やや語調を荒げて不機嫌に言った。
「ところで、スーザン、君は幾ら払ったんだい?」
ケンはとんだ仕事を引き受けたことを後悔し、感情を露骨に表しだしたスーザンに向かって冷静に訊ねた。
「10ドルよ!」
スーザンは吐き捨てるように短く言った。
「オーケイ、じゃあ僕も10ドル払おう!」
1時間以上に渡る口論にようやく終止符が打たれた。
スーザンと車掌は引き上げて行った。
ケンは、喉がカラカラに渇いていることに気付き、ローザンヌで汲んでおいた水を〝ヴィシ〟のマークが入ったミネラルウォーターのボトルから、美味そうに一口飲んだ。
二人のアメリカ人の青年は、この騒ぎを物ともせず、カーテンをぴったりと閉ざして、すでにグッスリ眠り込んでいたが、ケンの下のベッドのオーストラリア人の牧師は、途中から起きて来て、事の成り行きを一部始終見守っていた。
「よかったね。私も君の言ってることが正しいと思うよ。でも、今晩は本当に暑いよ。」
と言いながら、100㎏は優に超えていると思われる全身を金色の体毛で覆われた体を揺すりながら、右の手の掌で額の汗をぬぐった後、
「そのヴィシ、一口もらえないかね?」
と、何やらその大きな体には似つかわしくない、照れたような表情でたずねた。
翌朝、ケンが短い眠りから目覚め、コンパートメントから通路へ出てみると、開け放たれた窓から吹き込む涼しい朝の風が、昨夜の蒸し暑さとは打って変わってケンの体中に染み渡った。まだ完全に昇りきらぬ太陽が、車窓に広がる荒涼とした景色を金色に染めているのを眺めていると、スペインへ来たという実感が急に湧いてきた。
ふと横を見ると、スーザンがすっかり身支度を済ませ、昨夜の疲れも見せずに凜として、朝日を受けながら何やら遠くを見つめて立っていた。
風にブロンドの髪をなびかせているその横顔を見ていると、何だか急にジェニーのことが思い出された。
列車の中で知り合った束の間の友人たちに短い別れを告げると、ケンはマドリッド駅のホームに降り立った。ヨーロッパの各都市から間断なく出入りするTEEやスペイン各地から到着するローカル列車から降り立つ人々で、プラットホームはごった返していた。
ケンは、カーニバルのような喧騒に湧きかえる人ごみをかき分け、やっとの思いで駅の構内へ重いリュックを背負ってたどり着いた。
構内もホーム以上の人々で覆い尽くされていたが、その古いゴチック式の伝統様式を取り入れた高い天井の駅舎は、かつてのスペインの栄華を感じさせる立派なものだった。
マドリッドの駅前広場は、駅構内の人ごみとは打って変って閑散として広々としていた。それは、いつかテレビで見た中国か、北朝鮮の軍事パレードを行う広場のようだとケンには思われた。
その当時、スペインはまだフランコ将軍の独裁政権下にあり、国としての統制は徹底していたようである。ケンは、スペインは初めてであったが、軍事政権と聞くと共産国のもっと暗いイメージを抱いていたが、駅前の広場の閑散とした光景以外には、そのような彼が抱いていた危惧は瞬く間に吹き飛んでしまった。
拙い習いたてのスペイン語でバスを乗り継ぎ、ケンはマヨール広場へとたどり着いた。
マドリッドの街は、思ったよりも活気にあふれていて、近代的なのにケンは少し驚いた。祖母から聞いていた祖母の祖国スペインのイメージとは少し違うような気がした。
だが、燦々と降りそそぐ太陽の光とどこまでも澄みきった真っ青な青空は幼い頃から祖母より聞かされていたのと全く同じだった。
ケンは、旅行案内書に出ていた世界一安いというホテルマドリッドに、街中を半日歩き廻ってようやく辿り着いた。
ホテルの受付には、白髪交じりで日に焼けた目の表情が読み取れないほどの皺だらけの老婆が座っていた。
その老婆は、ケンの顔を見るや、たった今一つだけ部屋が空いたところだが、掃除が終わってないのでもう3時間待つなら貸してあげようと、無愛想に早口のスペイン語で、ケンの瞳を皺の奥に隠れた昔は美しかったであろうと思われるコバルトブルーの小さな瞳で見つめながら言った。
このホテルには、安いということもあってか、世界中から若者が集まっていて、この老主人によれば、永い人は5年以上も住みついているということだった。
この話をホテルの女主人から聞いたとき、マドリードはよほど住み易い街に違いないとケンは思った。
後で分かったことだがこの老婆には昔、日本人の恋人がいたということで、日本人に対しては格別の好意を抱いていたようだった。
ある日、ケンが、カウンターのそばを通り過ぎようとすると、いつもの老婆が座っていて何やら、日本語で奥のほうに向かって呼び掛けていた。「ねこ、ねこ、、、」と……
ケンは、その老婆が日本語を話すのかと思って、日本語で話しかけたが、彼女は何も反応は示さなかった。
ただ、彼女は、自分の飼っている猫に “ねこ” と名前をつけたのだという。これも、昔付き合っていたボーイフレンドの思い出のためかとケンは一人思った。
老主人が言うように、ケンは背中のバックパックをホテルに預けると、今度は軽い足取りで今たどってきた道をゆっくりとマドリードの街中へと戻って行った。
どこへ行こうというあてもなかったので、とりあえず先ほどのマヨール広場へ戻ってみることにした。
古い石畳に太陽が反射して気温は優に40度は超えているように思われた。
ただ、道端には、いたるところに大きな街路樹が植えてあり、ところどころに涼しい木陰ができていた。
木陰の下には、たまに古惚けた白いペンキの剥げたベンチが見かけられ、暑さに耐えきれない人々が此処かしこに涼をとりながら、何やら楽しげに話している様子を見て、ケンは何だかやっとスペインに来たという気がした。
いつもは、人でにぎわっているマヨール広場も、さすがにこの炎天下では人影もまばらであったが、ここでも広場の中にある回廊の各所に備えてあるベンチやカフェのパラソルの下には、やはり話に夢中の老人や若者が、かなりの数で見かけられた。
ケンは、一番人気のないカフェの軒下にある涼しそうな椅子を選んで、腰を下ろした。
しばらくすると、髭の剃り残しのある額は禿げあがってはいるものの多分20代だと思われるウェイターが、やや不機嫌な様子でにケンに近づくと、「何にしますか?」とだけ聞いた。
ケンは、「ウン・コカ、ポルファボール」と答えたが、これがスペイン語か、イタリア語か迷ったが、相手には通じたようであった。
これまで、ヨーロッパの各地を転々と浮浪者のような旅をしてきたケンには、どんな言葉であろうと相手に通じればいいといった開き直りの気持ちがあった。
また、実際言葉なんて、どこの国の言葉であろうと、何も文法とか形式とかに拘る必要がないことは、ケンもすでに子供のころから学んでいたことでもあった。
女主人の言うように、3時間以上時間を潰してホテルへ戻ってみると、ケンの荷物は、受付の前をまっすぐに伸びた廊下の端にある一番北側の薄暗い部屋にもうすでに置かれていた。
ケンは、部屋に入るとすぐに荷物を解き、今までに溜まった汗臭いシャツやら下着をシャワー室の浴槽の中に放り込むと自分の身体を冷たいシャワーの水で浴びながら、備え付けてあった古びてひび割れた泡の立たない石鹸で衣類とともに洗った。
久しぶりのシャワーで、ケンは身も心も洗れたような清々しい気持ちになった。
2枚しかないジーンズもこの際思い切って洗ったものの、果たして夕食までに乾くものかと少し心配になったが、どうしようもなく、仕方ないなと気を取り直して、思い切ってこの際すべての衣類を洗うことにした。
シャワー室の中にあったハンガーに無造作にシャツやジーンズを干すと、ケンは夕方まで束の間のシエスタと決め込んで、まっ白いシーツの間に身体を滑り込ませたが、壊れた木製のシェイドから差し込む光は、やはりイギリスや北欧のそれとは違って眩しかった。
外は、優に40度は越えていると思われるマドリッドの過酷な夏の太陽も、分厚い石造りの建物の中にまでは入ってこれず、室内は乾燥した気候のため、むしろひんやりとして涼しかった。
壊れたシェイドから差し込む木漏れ日は、子守唄のように彼の全身を柔らかく包み込み、その優しさと長旅の果てにようやく辿りついたまともなベッドの心地よさで、ケンはすぐに深い眠りに就いた。
どのくらい眠っていたのだろう、父にもらったケンのセイコーの腕時計はもうすでに午後6時を示していた。
まっ白いシーツに包まれ、少し休んだ身体は、全身の筋肉がやや硬直していた。彼は、ベッドの中で大きく背伸びをすると、もう一度冷たいシャワーに飛び込んだ。今までの疲れはすでにどこかへ飛んでしまって、またいつもの彼に戻っていた。

先ほど心配していたジーンズは、糊をつけたかのようにカリカリに乾燥していて、両足を通すのに一苦労した。
ホテルの小さなロビーへ行ってみると、そこには既に十人ほどの若者が集まって、様々な国の言葉が飛び交っていた。その中に日本人と思しき青年を見つけると、ケンは流暢な日本語で話しかけた。
一瞬その青年は、その痩せた無精ひげとは対照的に日本人にしては涼しげな大きな瞳でケンをいぶかしげに見つめると、「日本語うまいな!」と感心したように、ケンに話しかけた。
ケン、いつものように自分の生い立ちなどを手短に説明したが、その青年は急にケンに対して同じ日本人として親近感を覚えたようであった。外国に独りでいると殆どの日本人は日本人を避けるきらいがあると、ケンは今まで思っていたが、彼は少し違っているように思えた。
彼の風貌はヒッピーそのものであったが、彼の語る言葉は、禅僧あるいはケンが小さいころから通っていた教会の牧師のようにも思えて、ケンは懐かしい思いが込み上げてくるのを覚えた。
まさかマドリッドの下町にあるこんな安宿で日本人に会うとは、何か奇妙な感じがした。ヨーロッパで日本人に会うことが珍しいこの時代に、ましてや日本から遠く離れたスペインの観光コースからはかなり外れた小さな名もない安宿で、一人の日本人に会ったことがことさら感慨深く思えた。
この牧師のような語り口の男は、”イケダ”と名乗り、スペインにはもう5年以上も前に来たという。
この宿には、もう既に3年近くは住んでいるとのことであった。
この男はその風貌いでたちから、かなり年を食っているように見えたが、実際はまだ30歳足らずの青年であることをケンは後で知った。
これも後に聞いた話だが、彼は周囲の人の話によれば日本の東京大学在学中に、フラメンコギターに取り憑かれて、マドリッドへやって来て、そのままこの都市へ住みついたのだという。
しかしこの人物は、風貌から見てもとても日本で一番難しい大学の学生とは思えなかった。
ケンは、ただイケダさんは何か哲学者のようだという印象を持った。
彼は、昼間はホテルで何もせずにゴロゴロして、時折やって来るケンのような親切な若者から食事をご馳走になるとき以外は、ほとんど寝ていた。
夜になると、ギターを抱えて繁華街へ出かけては、路上でフラメンコギターを弾き、観光客に金を恵んでもらって、あくる日のホテルに充てるという生活を送っていた。
ケンは、一度だけ、ホテルにイケダと二人っきりで居るときに彼のギターの演奏を聞いたことがあった。
彼は、音楽に余り興味がある方ではなかったが、ただイケダの右の5本の指のつまびく弦の奏でる魔法のような音色に深い感動を覚えた。
「イケダさん、いつもギターだけで稼いでいるんですか?」
ケンは、彼の不思議な生活に少し立ち入ってみたいような衝動にかられた。
イケダは、上の方の前歯が一本欠けた口元でニヤッと笑ってみせた。
顔中ひげに覆われた、強面とはそぐわないアンバランスな表情であった。
「そればかりじゃないさ……」
とイケダは半分使ったプラスチックの容器に入った醤油を指さして、
「こないだ、日本人の旅行者からもらったんだ。時々こんな珍しいものをスペイン人に高く売りつけるんだ。ギターよりは金になるよ……」
と、再び前歯の欠けた歯をむき出しにして笑ってみせた。
ケンは、こんな大らかで、気取りのない天衣無縫とも言えるイケダにしだいに惹かれていく自分を感じ取っていた。
二人は、何か惹かれあうものがあるらしく、ロビーで会うといつもケンのこれまでの旅行の話やら、イケダの過去の経験やら冒険談めいた話で盛り上がった。
ある夜、イケダはケンを食事に誘った。ケンも金がないことを知っていたイケダは、ケンに向かって、
「心配するな、今日はおれのおごりだ。但し、マヨール広場で少しだけギターの演奏に対しての恵みを期待しているが、むしろこの醤油が売れればの話だがな.......は、は、は、は........」
といつものように、前歯の欠けた歯をむき出しにして快活に笑った。
その夜、ケンはイケダの後をついてマヨール広場まで行って、イケダのフラメンコギターの演奏に聞き入っていると、アメリカから来たと思われるカップルが寄ってきて、金髪のを肩まで垂らした少しほろ酔い加減の痩せた背の高い男のほうが、こともあろうに100ドル札をイケダのギターケースの中へと無造作に放り込むと、
「グッド、ジョブ!」
と言い放って、連れの若い女とその場を立ち去った。
ケンとイケダは、びっくりして顔を見合わせると、先ほどの男の酔いが醒めて、戻ってくる前に一目散にその場を切り上げた。
マヨール広場を後にした二人は、イケダの行きつけの、小さなレストランで食事を摂ることにした。レストランとは名ばかりのホテルから数百メートルほどにある小さな店であった。店内には、二人以外にまだ誰も客はいなかった。
二人が店に入ると、その店の主人の娘だという赤毛のやけに眼だけが大きいひょろっとしたケンよりは若いと思われるウェイトレスがやって来て、
「まず飲み物は何にするか?」
と無愛想な口調で聞いてきた。
イケダは、その娘とは顔なじみらしく、いつもの歯の欠けた笑顔で「ビール」とだけ日本語なまりのスペイン語で短く答えると、
「マリア、こちらはケンだ。」と付け加えた。
ケンは、短く「ケンです。よろしく」と英語で言ったが、
マリアはケンに作り笑いをするだけで、何も言わなかった。
そして、ケンの方に顔を向けると首を左のほうへ少しだけ傾けてケンの注文を待っていた。
ケンは、咄嗟に「ウォーター、プリーズ」と言ったが、娘には何の反応も見られなかった。ケンは、ここがスペインであることを今更ながらに思い知った。
ホテルと言い、バスやらタクシーの運転手、通行人すべてが、マドリッドに来て以来ケンが会ったほとんどの人が、英語が話せなかった。本当に全く、簡単な言葉でさえ通じなかった。ケンは、今更ながらに、もっとスペイン語を勉強しておくべきだったと後悔した。
結局、ただの水を注文するだけで(もちろん日本のように無料の水のサービスはない)、英語、フランス語と使ってみたが、まったく効果はなかった。ケンは、ソルボンヌのドームでの最初のシャワーのことを思い返していた。
フランス語は、スペイン語と同じラテン語だと理解していたケンであったが、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語は、やはり微妙に違っていて、言葉そのものが全く違うものもあるが、所詮は同じ穴のムジナだとケンは、思った。
結局ギブアップして、スペイン語の発音は日本語風であるが、堪能であるイケダに救いを求めた。
イケダは、「アグア、ポルファボール」と流暢でもない日本語風のスペイン語でさりげなくケンのために水のボトルを注文してくれた。
ケンは、何だ “アグアか、そんなの英語のアクアと同じだ” と気がついた。言葉もスペルも近いし、“何でこんな単純なことが分からないのだろう” と少し自分に腹が立った。
ケンとイケダは、お互い何とはなしに惹かれあうものを感じて、ほとんど毎日2人で過ごすことが多かった。ある日イケダは、先日行ったレストランの娘マリアとその友達たちに闘牛に誘われたのでケンにも一緒に来ないかと訊ねた。勿論、ケンは闘牛など生まれて初めてだったのですぐにその誘いに乗った。
2人はマリアの父の店の前で炎天下に約1時間もまたされて、ようやくマリアは、その友達だという同じ年頃のブロンドの髪をポニーテイルに束ねたナタリーという娘を伴って現れた。
マリアは、別に遅れたことを詫びるでもなく、ただ、にこやかにケンとイケダに向かって「ケ、タル?」と問いかけた。
「ムイ、ビアン」とイケダは、いつものように欠けた前歯をむき出して照れ笑いしながら答えたが、彼女は、イケダの挨拶を遮るように、すかさずヘアードレッサーの仕事をしているというナタリーを2人に紹介した。
その笑顔は、先日初めて会った時とは打って変って、朗らかで陽気なスペイン娘になっていた。
その日、4人はマドリッドの郊外にある闘牛場へと向かった。
その闘牛場は、かなりの歴史を誇るものらしく由緒あるスペインきっての闘牛場だと、ケンはマリアがイケダに言うのを聞いていたが、想像していたものよりやや狭く貧相な感じを受けた。
しかし、一旦、赤と金刺繍で飾られたタイツと肩章の付いた煌びやかなマタドール服にぴったりと包まれた引き締まった身体のマタドールが現れ、ムレータを翳しながら、闘牛場の中央に立ち観衆に向かって優雅にお辞儀をすると、闘牛場を埋め尽くしていた観衆は総立ちになり、その人々の昂奮と歓声で廻りの音はすべてかき消され、ケンは鳥肌が立つのを覚えた。
闘牛士の中でも、マタドールに昇り詰めるには長い下積み生活を経て、ようやく闘牛士全体の1割程度が到達できる狭き門である。
闘牛の時、使用される赤い布は ”ムレータ” と呼ばれ、牛は赤いものを見ると興奮するとケンは聞いていたが、実際は牛の目は色を区別できず、色でなく動きで興奮をあおっているということを博学のイケダが教えてくれた。むしろ、赤い布で興奮するのは観衆の方であるようだ。
4人は、闘牛で興奮した気持ちを冷ますために、闘牛場のそばにあるプールでその日の残りを過ごした。ケンは、久しぶりにパリのあの出来事以来、ゆったりとした幸福な時間を仲間の3人と共に心行くまで満喫した。
その夜は、イケダのおごりで、マヨール広場の一角にあるマドリッド随一のフラメンコが見られる小さなレストランへみんなで行った。そのレストランは、マヨール広場の大通りから広場へ通じる石の階段を登り切った広場の入り口の左側にあった。
ようやく小さな大人が一人通れる程度の背の低い分厚い木製のドアを開けると、その扉の高さとは対照的に高い天井にケンは驚いたが、中はもう既に老若男女で埋め尽くされ、いままで聞いたことがないようなスペイン語が飛び交い、ロンドンのパブのように煙草の煙が充満していた。
百年以上も経っていると思われるレストランの石畳の床は、中央が窪んで擦り減って、もともとは真っ白い漆喰で塗り固められた壁は、煙草のヤニで黄色く変色していた。
蝋燭の薄暗い光の中に突然現れたこの大きな空間は、四方にある大きな石造りの柱の周囲に40〜50程のテーブルが並べられており、約30平米もあると思われるその中央のホールは一段と高い丸天井になってた。
4人は、柱のすぐ横の小さな木造りのテーブルを何とか見つけると、サングリア(Sangría)を早速、ピッチャーで注文した。
今日の闘牛やプールでのケンが見せた華麗な飛び込みを真似してイケダが顔から飛び込んでその日焼けした顔が真っ赤に腫れ上がって暫くは今にも死にそうだったイケダのことで、アルコールも手伝ったせいか4人は腹を抱えて笑い転げた。
1時間ほど経って、ホールでは、突然フラメンコギターが奏でられ、cantaor(カンタオール)の魂の奥から響くような歌声と共に、真っ赤なドレスに身を包んだbailaora(バイラオーラ=女性の踊り手)が突然現れた。
pallilos(パリージョ)を両手でリズムを取りながら、ホールの中心に躍り出た踊り子は、つま先や踵で床を踏み鳴らしながら、pallilosを打ち鳴らす両手を交互に上下に翳しながら、優雅に上半身をくねらして激しく踊った。
観客は、Jaleo(ハレオ=オーレなどの掛け声)とPalma(パルマ=平手で甲高く叩く手拍子)で、場を盛り上げ、それに呼応するかのように踊り子は、その額に汗の玉を光らせながら、ますます激しく踊り続けた。
その踊りと、Jaleo、Palmaは何時間も続き、いつしかケンもその両手が真っ赤に腫れ上がるのも気づかずにbailaoraのリズムに合わせて叩きつづけた。
熱気に満ちた踊りを見ながら、イケダも秘かに恋い焦がれているマリアが傍にいるだけで、今までになく幸せそうだった。マリアとナタリーは、久しぶりに会って二人とも若い娘らしくナタリーの新しいボーイフレンドのことやらファッションのことでサングリアを飲みながら、話が弾んでいるようであった。この屈託ない二人を眺めながらケンは、ふとジェニーのことを思い出して、パリでの再会に胸の奥が少し熱くなるのを感じた。
イケダは、その日以来2日間帰って来なかった。南米から来たというパウロがあわただしく、階段をかけ昇ってドアを突き破るように入って来た。
「イケダが死んだ! 2日前の晩、マヨール広場での大通りで酔っぱらって車にひかれたんだ……」
パウロは、震えながら友人の死を告げた。
パリに帰ったジェニーは、ジュネーブでの短い幸せな出来事を誰に話していいものか迷っていた。
とりあえず、ケンの親友シャルルに会って、おかげでケンと無事に再会を果たし、また、二人の気持ちを確かめ会ったことを報告した。
シャルルは、自分のことのように喜んでくれた。
ジェニーはケンから絵葉書を一枚受け取った。
それには、マドリッドの体験やケンの知り合ったばかりの友人の突然の死のことも書いてあった。ケンは一週間したらパリへ帰り、ジェニーとの再会を毎日楽しみにしていることを最後に添えていた。
シェニーにとって、パリでの生活は毎日が今までよりも長く感じられたが、一週間後には、最愛の人と再会出来るということが分かって以来、一層充実したものに感じられた。
一方、ケイトはあの日の出来事以来、ケンが自分の前から姿を消し、ヨーロッパの旅へ出たことを知り、すくなからぬ精神的なショックを受けていた。彼女もケンを心の底から愛していた。
ケンがパリを離れる数日前までは、幸せの絶頂にあったのに、突然、不幸のどん底に突き落とされたことを彼女はどうしても認めることができなかった。
ジェニーは、そんな彼女の激しい心の葛藤を知る由もなかった。
ジェニーは、親友であるケイトには、自分たちのことを話しておく必要があると考えた。二人は久しぶりに揃って買い物に出かけた帰り、シャンゼリゼ通りの「カフェド・パリ」に立ち寄った。
注文を済ませると、ジェニーは嬉しそうにケイトに向かって言った。
「ケイト、あなたケンが帰ってくること知ってる?」
「えっ?」
ケイトは、突然の話題で何のことだかすぐに理解することが出来なかった。今まで、ケンのことはジェニーとの間では、彼女がケンに気がありそうだということに感づいてからは、暗黙のうちに口にしなくなっていた。だから、お互いにプライベートな生活にはほとんど入り込まないようにしていた。
「今日、ケンから手紙が来たのよ。」
ジェニーは、ケイトの顔色を窺いながら続けた。
「実はね……、こないだ10日間ほど、私もパリを離れたでしょう。あのとき、ケンとジュネーブであったのよ。」
ケイトは、突然の出来事に頭を後ろから急になぐられたような衝撃と精神的な動揺を覚えたが、いつもの優しい理知的な表情を変えずに黙って聞いていた。
ジェニーの口からこれから何が飛び出すかも、頭の中でちゃんと計算できていた。
胸は鼓動の高まりと嫉妬とで張り裂けんばかりだった。ジェニーはケイトのこのような心の変化には全く気付かずに先を続けた。
「ジュネーブで、私たち二人はこれまでお互い誤解し会っていたことに気付いたのよ。つまり……本当は二人は愛し合っていることを隠していたのよ。お互いから……」
ケイトは、突然、激しい目まいを覚えて、その場に崩れてしまいそうになるのを必死の思いでこらえた。
また、この時ばかりは、普段、信仰心の強い彼女も、神の存在を疑った。ケンに対する気持ちは、誰にも負けない彼女だったが、ケンの自分に対する気持ちは、ケンがパリを離れたときから既に分かっていたつもりだったのだが、このような結末になろうとは予想はしていなかった。だからなおさら納得できなかった。
「でも、ジェニー……」
ケイトは、喜びの絶頂にあるジェニーを正面からきりっと見据えて、冷酷に言った。
「ケンは、私のことは何も話さなかったの?」
「えっ?」
ジェニーは、不吉な予感が頭の中で過ぎるのを感じた。
「ケンと私との関係よ……。私たち、もう、他人じゃないのよ。ケンがパリを離れる2日前に、私たち結ばれたのよ。」
ケイトは、ジェニーの顔から血の気がさっと引いていくのを冷たく見つめていた。
「ケンって、とんだ女ったらしね!」
ケイトは、ジェニーの悲しみに歪んでいく顔を眺めながらとどめを刺した。
ジェニーは、全く降って湧いたような突拍子もない話に最初はにわかに信じ難かったが、ケイトの自信ありげな表情を見ているうちに、ケンに対する信頼が、急速に崩れていくのを感じた。
「そうだわ。ケイトの言うのが本当かもしれない……。だって、彼女の方がずっと大人で、私なんかよりもっと魅力的なんですもの……」
ジェニーは、知らない間に涙が頬を伝って落ちているのを気づかずに心の中で反芻していた。
「でも、あれだけ二人で誓い合った仲だからそんなはずはないわ……。ケンに会って、確かめなければ……」
ジェニーは、伯父のポルシェをガレージから出すと、誰にも行き先を告げずに猛烈なスピードでモンパルナスの屋敷を飛び出していった。
ケンは、マドリッドでのイケダの死に深い衝撃を受け、暫くは急に降って湧いた悲報にどのように対処していいものか心の整理が付かなかった。たが、スペインの乾燥した気候と根っからの楽天的な人々が深い悲しみを少しづつ和らげてくれた。それと同時に、最愛の恋人に再会する期待感が悲しみを打ち消してくれた。
前もってジェニーに連絡しておいたように、予定通りリヨン駅に着いた彼は、胸を躍らせながらジェニーの家の公衆電話のダイヤルを回した。
これまで、できる限りの禁欲生活と精神の帰依を堪え忍んできた彼は、嬉しさでダイヤルを回す指先の震えをようやくの思いで抑えながら、ダイヤルを回し続けた。
「アロー!」
電話口に出た、お手伝いの中年の女性はちょっと待つように言った。しばらくして、反対側の受話器からは、意外な聞き覚えのある声が聞こえてきた。
「ああ、ケンね……。あなたの電話を待ってたのよ……」
いつもとは、違う響きのケイトの声であった。
「やあ、ケイト、久し振りだね。元気だったかい?」
ケンの中で、ケイトに対する感情的なわだかまりはもうすでに消えていた。
「ケン、冷静になってよく聞いて欲しいんだけど……」
ケイトは、ケンの言うことには何も答えずに続けた。
「ジェニーは、もういないのよ……」
と、ケイトはかすれたような低い声でしゃべった。
「えっ? 何だって?」
ケンは、ケイトの言う意味が分からずに、ジェニーが気でも変わってアメリカにでも帰ったのかと思った。
「ジェニーは……、ジェニーは、あなたに会うためにマドリッドへ向かう途中ピレネーの山の中で自動車事故に遭って死んだのよ……。死んじゃったのよ!」
ケイトは涙で声をつならせながらも最後の言葉だけ、叫ぶようにしっかりと言った。
ケンは、しばらく受話器を持ったまま、その場に立ちつくしていた。
リヨン駅では、ジュネーブに向かうTEEの出発を告げるアナウンスが流れていた。
「アロー、アロー、アロー……。
ケン! 聞こえているの?
アロー、アロー、アロー…… 」
駅の喧騒にかき消されて、ケンの右手の中の受話器からケイトの声だけがいつまでも響いていた。
「アロー、アロー、アロー……。
ケン! 聞こえているの?
アロー、アロー、アロー…… 」
「アロー、アロー、アロー…………
…………………………………………
………………………………………… 」
翌日、ケンはソウルへ向かうKEの小さな窓から、パリの街を眺めていた。気付かないうちに空から見るパリの街は色づき初秋の佇まいを見せていた。
セーヌ河畔には、ケンが青春を燃焼させた、ノートルダム寺院、カルチェラタン、コンコルド広場、その向こうにはエッフェル塔が見え、パリの街は、ケンが初めて訪れたときと全く変わらない姿で、眼下に広がっていた。
これから、何十年、いや、何百年もの間、この街は変わらずに世界の人々に憧れの街であり続けるのだろう。
だが、ケンはもう二度とこの街に戻って来ないだろうとふと思った。
ケンと乗客400人を乗せたKEは、パリの上空をゆっくりと別れを惜しむかのように旋回するとソウルへ機首を向けて飛んで行った。
お問合せ
ご意見・ご感想などお聞かせください。