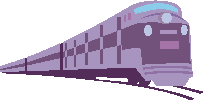「ユーレイルパスの延長をお願いします……」
ケンは、リヨン駅の出発窓口カウンターの前で、無愛想なカギ鼻の中年の駅員に言った。
「パスポート。」
駅員は、下を向いて、他の書類にサインやらスタンプを押しながら、顔を上げようともしなかった。
ケンは急いで、パスポートを取り出そうとしたが、ポケットではなく、リュックに入れていたことに気がつき、リュックをかかえ上げるために後ろへ手を伸ばしたが、つい先まで、後ろに置いたばかりのリュックの姿形は、もうどこにもなかった。
『あっ! しまった!』
咄嗟に彼は、置き引きにあったことに気付きあたりを一生懸命見渡した。50mほど先の駅の構内を彼のリュックと同じものをかついで、足早に歩いている男の姿を認めた彼は、大声で「泥棒!」と叫びながら、その男を追いかけた。
その男は、ケンが後ろから追って来ているのに気がつき、全速で走り出した。ケンは、人混みの中を思うように走れず、一瞬、男を見失いそうになり、もうダメかと思った。人垣の中をかき分けて行くと何と、その男は、リュックを肩にかついだま
ま大理石の床の上に倒れているではないか。
その男の側には、口ひげと顎ひげをたくわえた、インド人とその友人と思われる2人のアラブ人が悠然と立っていた。
ケンは、息せき切ってようやく、その場へ辿り着いた。
「このリュックは、お前のか?」
2人のアラブ人のうち背の高い方の左足にギプスを巻いた男が流暢なフランス語で聞いてきた。
「あ、ああ!」
ケンは、まだ荒い息をしながら、呼吸を整えようと努力した。
「危ないところだったぜ。もう少しの所で、逃げられるところだった。アフタブが、石膏で出来た足を投げ出さなけりゃ、こいつはもうとっくに、ここからおさらばしていたところだ。」
浅黒い肌をした鼻の高いインド人が、訛りのきついフランス語でまくしたてた。
「ああ、助かったよ。ありがとう。」
ケンは、インド人と2人のアラブ人の顔を交互に見て礼を言った。
「ところで、こいつどうする?」
背の低いがっしりした体つきのアラブ人がケンに聞いた。
ケンのリュックを盗もうとした男は、まだ、大理石の床の上に座り込んだまま、不安な顔をして事の成り行きを見守っていた。
「そうだな……。こうして、リュックも無事戻って来たことだし、もう放してやってもいいんじゃないかな……」
とケンは、別にこの男に大した恨みも持っていない様子でさらりと言ったので、むしろ、他の3人が驚いたような顔をして、お互い顔を見合わせた。
「そうか、お前がそう言うなら、それでいいさ。」
と背の高い右足にギプスを巻いたアラブ人が、肩をすくめながら言った。
「OK、もういいぞ。」
インド人が、そう言いながら座っている男の尻を右足で軽くけっ飛ばすと、男はおどおどしながら、
ケンに「メルシー、ボク。」と言うとあわてふためいて一目散に走り出し、あっという間に姿が見えなくなった。
「本当にありがとう。僕の名はケンだ。」
ケンは、3人に交互に右手を差し出しながら言った。
「俺は、アフタブ。」
ギプスの男がケンを握手しながら言った。続いて、
「ファーレス。」
背の低いがっしりした体格のアラブ人は短く言った。
「俺の名は、シャムだ。でも、ケン、よかったな。俺もアムステルダムで一回やられたことがあるんだ。君は、パリは、まだ短いのか?」
他の2人に比べると貧相に見えるインド人は、他の2人よりも好意的だった。
「いや、そんなことはないけど、こんな経験は今日が初めてだ……。本当に最初は、もう、これで終わりかと思ったよ……」
「これからは、気を付けるんだな。じゃ、俺たちはここで失礼するぜ。」
アフタブは、ファーレスを促すと右足を引きずりながら、シャムに「オ・ルボワール。」と言うと、その場を立ち去った。後には、ケンとシャムが残った。
「ケン、君はこれからどこへ行くんだ?」
シャムは、顎ひげを撫でながら聞いた。
「ああ、特に目的地はないんだが、これからヨーロッパの街をあちこち訪ねてみたいと思っているんだ……」
ケンは、床に投げ出されたままのリュックを背負いながら答えた。
「そうか、俺も実は、これからTEE(ヨーロッパ特急)で旅に出ようと思ってたところなんだ。もしよかったら、俺と一緒に来るか?」
シャムは、ケンの目をじっと見つめながらたずねた。
ケンは、彼の目をしばらく見つめ返していたが、その瞳には、一点の曇りもなさそうだった。
「いいだろう。じゃあ、一緒に行こう。」
二人は、それぞれ背中に重いリュックを背負ってホームへ向かって歩き出した。
アムステルダム、デュッセルドルフ、ミュンヘンを経て、パリを出発して1週間目にケンとシャムはフランクフルトへ着いた。
フランクフルトの街は、ケンが想像していたよりも小さく、印象的だったのは、ドイツのどこの都市でもそうあるように街が驚くほど整備されていて美しい反面、人通りが少ないということであった。
町中の人々がバカンスで出かけているとしても、街の大きさに比べて、メインストリートにも、さほど人気がなく、ただ建物だけがひっそりと建っているという感じであった。二人は、駅前のメインストリートを真っ直ぐ歩いて行った。駅から4〜500 m程、歩いた所に、星印のない古ぼけた小さなホテルを見つけ、その前で二人は立ち止まった。
「ケン、今夜はここにするか?」
シャムは、ホテルの看板を見上げながら言った。
「OK。でも念のために、まず、料金を聞いてみようじゃないか。」
ケンは、突然の思いつきでパリを飛び出したので、余り金に余裕がないことを心配していた。
シャムが、先にホテルの中は入って行った。カウンターには、でっぷりと太り、油でてかてか光った、赤ら顔をした、中年の男が座ってポルノ雑誌に見入っていた。
「今晩、泊まりたいんだが、一晩いくらだ?」
シャムは、無造作に訊ねた。
男は、突然の客に一瞬、驚いた様子だったが、
「一人、20マルクだ。」
ホテルの入口に重いリュックを背負ったまま立ちつくしているケンをちらりと見て言った。
「ちょっと、高いんじゃないか……。2人で、20マルク※でどうだ?」(※1マルクは当時で、約70円)
シャムは、その男の青い瞳をみつめながら言った。
男は、ケンとシャムを値踏みでもするかのように、しばらくじろじろと見ていたが、やがて
「よかろう。2人で30マルクだ。」
とぶっきら棒に短く答えた。シャムは、ケンの方を振り返ってケンの反応を見たが、ケンは右の親指を黙って立てて見せた。二人は、カウンターの男からカギを受け取ると、重いリュックを背負ったまま、みしっみしっと軋んで、今にも壊れ落ちそうな、古い木製の階段を昇って行った。
部屋は、思ったほど狭くなかったが、ベッドはセミダブルのベッドが一つ置いてあるだけで、シャワーは部屋にはなかった。シャムが、再びカウンターまで降りて行って、聞いて来た結果、シャワーは共同のものが一つだけ、各フロアーにあり、更に2マルクの使用料が必要との事であった。
パリを出て以来、1週間、昼はヨーロッパ各地の名所、旧跡を訪ね、夜は宿代を節約するために列車の中で寝る生活を送って来た2人にとって、このホテルは、安宿とはいえ、シャワーもベッドもあるし、久し振りの最高の贅沢であった。
ケンは、リュックを床の上へ下ろすや、一目散にシャワー室へ飛び込んだ。お湯のコックを捻ってもなかなか湯は出て来なかった。多分、節約のためにボイラーの電源を切っているに違いない。ケンは、そう思いながら、仕方がないので水を思いっ切り出すと頭からかぶり、石けんの泡をいっぱいたてながら体中の垢を落とした。
一週間分の汚れが、石けんの泡と共に白いホーローの浴槽の排水口へと渦を巻いて流れていった。ケンが、上半身裸で、バスタオルを首から両肩にかけて垂らしたまま部屋へ戻ってみると、シャムはベッドの上にあぐらをかき、例によって、世界中のインド料理店の所在地を表した案内書を広げて、フランクフルトでの一番近い店を探している最中であった。
ケンは、この奇妙な南アフリカ国籍のインド人と旅を始めて、一週間近くなるが、まだ彼の事を十分理解していなかった。
このインド人は、どんなに空腹であっても決してインド料理以外は口にしないし、ましてやマクドナルドのハンバーガーなどは、体を縄で縛り上げて、無理矢理に口の中へ押し込んだとしても、ハンバーガーを飲み込むよりは舌を噛み切ってしまうことが、容易に想像されるようなタイプであった。
「ケン、今夜は晩飯、何にしようか?」
シャムは、ケンが部屋に戻って来たのに気づいて案内書に視線を落としたまま訊ねた。
「えっ? 何にしようったって……、もう決まってるんだろう?」
ケンは、可笑しくって、吹き出しそうになるのを抑えながら言った。『何にしようかって? いつも、インド料理に決まっているのに……』と思いながら問い返した。
「今晩は、俺に付き合えよ。な、いいだろう?……」
シャムは、今度はケンの方に向き直って言った。
「でも、俺、辛い料理は、苦手なんだ……」
ケンは、インド料理の辛さよりは財布の中身の方が少々気になっていた。パリを出てまだ、一週間ほどにしかならないのに、手持ちの金は800ドル(*当時の1ドルは、約170円)ほどしか残っていなかった。
この1週間、シャムは毎日決まって2回、昼と晩は案内書に従って必ずインド料理店へ行き食事を取っていた。
ケンは、シャムが誘う度に、何かと理由をつけては、その誘いを断っていた。別にインド料理が嫌いという訳ではなく、むしろ小さい頃、神戸で育った環境のせいでインド人との付き合いも多く、当然、インド料理には慣れ親しんでいた。
ただ、節約のためにだけと金がないからという理由からであった。
そんなケンの気持ちをシャムは見透かしていたらしい。
「心配するな。今日は俺の奢りだ。それに、カレーだったら、ケン、お前だっていけるだろう……?」
ケンの顔を見つめながら、両方の太い眉をピクピクと愛嬌よく動かしながら言った。
「そ、そうだな。カレーなら……な。」
ケンは、何だか少し恥ずかしいような気がした。
シャムが、インド料理店の中へ入っている間、ケンは、店の外で待っていた。夏とはいえ霧雨の降るその夜は寒かった。
『セーターを持ってくればよかった。』リュックの底にまだ入れっぱなしになっているセーターを思い出すと、ポロシャツにジーンズという軽装がよけいに寒さを痛感させた。
ジーンズのポケットに両手を突っ込んで、寒さを我慢しながら店の前に立っていると、背の高い痩せこけた黒人が、近づいてきて、『1マルク恵んでくれ』という。ケンは、一瞬その男の目を見つめたが、その黄色くどろんと澱んだような悲しい瞳からは、何の反応もなかった。
ケンは、両手を突っ込んでいたジーンズの右のポケットから1マルク札を掴むと、男の白い掌にねじ込んだ。男は「ダンケ・シェーン」と言うと、ケンの前を通り過ぎ、立ち去っていった。その後ろ姿は、背が高い割には、何だか小さく見えた。ケンは、胸の中が熱くなり、何故か、急に悲しい思いがした。
心の中で、知らない間に子供の頃によく遊んでくれた、父方の祖父の事を思い出し、その黒人の後ろ姿にだぶらせていた。貧乏だったけど、いつも優しく一緒に遊んでくれたおじいちゃん、痩せていて背が高かった。ケンが寒さも忘れてぼんやりしていると、
「ケン、待たせたな。さ、早くホテルへ帰って食べようや。」
シャムは、たった今、レストランで作ってもらったばかりのカレーとナンの入った袋を両手に抱えて、出て来た。
ケンは、ホテルへ帰る途中、歩きながら、先程の黒人のことをシャムに話して聞かせたが、シャムは、
「そんなのにいちいち構ってたんじゃ、お前の財布なんか3日で空になっちまうぜ。」
と吐いて捨てるように言いながら、ケンの感傷的な気持ちなんか完全に無視しているようだった。
彼らはホテルに着くや、早速ベッドの横の小さなテーブルの上に、今持って帰ってきたばかりの包みを解きながら広げた。カレーの強烈な匂いが、ケンの鼻孔を刺激し、同時に胃袋が痛いほど、蠕動運動を始めるのが分かった。
ナンは、こうやって食べるんだと、シャムはケンに手本を見せてくれた。シャムは器用にナンでカレーをすくいながら話し出した。
彼は、インドのニューデリーの郊外の農村地帯で生まれ、10歳で家族に仕送りするためにニューデリー市内へ移り住んで停車中の自動車に新聞を売る仕事を始めた。時には、物乞いもしながら生計を立てた。
16歳になった時、新聞を買ってくれた人が、自分のレストランで働かないかと誘ってくれて、そこで2年間働くことになった。
18の時に、レストランの主人の紹介で南アフリカにあるインドレストランの皿洗いとして働き始め、半年で真面目さを買われコックに昇進した。
今では、そのレストランのシェフとして、腕を振るい、年に一回、こうして旅行をする為の長い休暇を取れる身分にまでなったという。
彼は、一生懸命働けば、誰だっていつかは報われるのだという強い信念をケンに対して語って聞かせた。
だから、ケンが今日道端で金を恵んだ乞食なんかに対しては、人間としての価値を認められないと言った。別に人種は、問題ではなく、真面目に働くかどうかが、一番大事なことなんだと……。
ケンは、ヨーロッパに於ける人種差別の状況を自分の周囲の人間の生活の中から肌で感じ取って、よく理解しているつもりだった。
特にアフリカ系黒人に対する差別は、アメリカ以上に厳しいものがあると彼は認識していた。
だから、シャムの人種的な差別はあまり関係がないんだという言葉には、いささか抵抗を覚え、反論したい衝動に駆られた。
パリで交際していた友人の黒人たちは、親友のシャルルを含め、何らかの差別を受けていた。
彼らのほとんどは、真面目な者たちばかりであるにもかかわらず、ただ肌が黒いというだけで、なかなか職を見つけることができないでいる。
南アフリカにしたって、同様なのではないか。いや、アパルトヘイトを信奉する一握りの白人に支配されている南アフリカは、もっとひどい状況だと聞いている。白人以外の人種は混血であれ、インド人であれ、彼ら白人の差別の対象である。
何故、差別される側のインド人であるシャムがそのような体制の中にありながら、人種差別に対する認識を持たないのか、ケンは不思議に思った。
しかし、その謎は、その翌日の朝になって自然に解けた。
ケンは、一週間振りにシャワーも浴び、シャムの好意により久々の満腹感を感じて、その夜は、ベッドの中に入ると、すぐに眠りについた。
明け方、6時頃、地震のような激しい揺れを感じ、驚いて目を開けると、セミダブルの同じベッドの上で、シャムは上を向いて寝たまま両手を胸の前で組み、体全体をバネにして宙へ飛び上がろうともがいていた。
シャムは、その動作に夢中で、ケンが目を覚ましたことには、まだ気付いていない様子であった。
ケンは、シャムのこの奇怪な動きを彼に気づかれないように、まだ、眠ったふりをしながら観察を続けた。よく観察してみると、シャムは何やら口の中で呪文を唱えているようだった。
彼のこの奇妙な、一種異様に見える癲癇発作のような行為は、実はインドのある種の宗教の朝の儀式だったのである。
ケンは、その後、シャムと色々なことを語り合ううちに、この男が敬虔なヒンズー教徒であり、博愛主義者であることを知った。
ケンは、この奇妙な博愛主義者を尊敬した。
二人は、その後、ドイツ国内のあらゆる都市や街を訪れてはインド料理を食べ、バスにも乗らずに歩き回った。
ケンは、このままいつまでも、この奇妙なインド人と旅をしたいと思ったが、
「シャム、君には、これまで色々と世話になったが、僕は、ここで君とは別れるべきだと思う。」
と、シャムの澄んだ黒い瞳をみつめながら、思い切って切り出した。
シャムは、しばらくケンの瞳をみつめ返しながら考えている様子だったが、ケンの気持ちを察したらしく、ケルンの大聖堂の前で、黙ってその細い右手を差し出すと、
「OK、ノープロブレム。また会おう!」と短く言った。
ケンは、その右手を両手でしっかり握りしめると、目にうっすらと涙を浮かべながら、
「シャム! ボン・ボワヤージュ……。オ・ルボワー」と最後の別れを言った。
二人は、半ば破れかけ薄汚れたジーンズにセーターという同じ出で立ちで、背中にはそれぞれ重いリュックを背負って茫然と
立ちつくしたまま、しばらくの間、その場を立ち去ろうとはしなかった。
ケンは、霧に煙るドーバー海峡を、カレーの港から出港した大型フェリーのデッキの上に立って、ひとり、感慨深げに眺めていた。
船の中は、彼と同じような格好をした、夏休みの休暇旅行を楽しむ、若者やら観光客で客室はおろか、デッキの上まであふれていて、とても座るスペースなどなかった。 ケンは、今まで陣取っていた真ん中のデッキの風の当たらない場所をトイレに立った隙にアメリカ人のケンと同年代のカップルに取られてしまった。
彼は、重いリュックを右肩にかつぎ、船内を探しまわったが、思うようにいい場所は見つからなかった。結局、アッパーデッキの風を時折降って来る小雨の中に立ち尽くす羽目に陥ってしまった。
夏とはいえ、やはりドイツと同じようにヨーロッパ特有のどんよりとした、厚い暗雲に覆われた空は、太陽の光を遮って、まるで初冬を思わせる寒さであった。
しかし、両親から屈強な体と強靱な精神力を受け継いだ彼には、たった一枚しか持っていないセーターを通して肌を突き刺すドーバーの寒風も歯が立たなかった。
彼は、寒風の中空と同じ位、どんよりと重い鉛色をした、ドーバーの海を眺めながら、ジェニーのことを思い出した。ジェニーはどうしているのだろう。多分今頃、あのフィアンセとコートダジュールあたりに避暑にでも行っているんではないだろうか。そんなことを考えながら、急に、ヨーロッパの中心は、やはりパリだと思った。別に、大きな理由はない。
フランスとイギリスは、ドーバー海峡を隔てて、たった40㎞しか離れていないのに、人々の生活習慣や気候はかなり異なっている。
この関係は、アジアで日本と韓国が同じような地理的位置関係にあるのに、文化や習慣に大きな相違を認めるのによく似ていると、彼は思った。
船が、高波を受け揺れる度に、水しぶきが空中に舞い上がり、風で霧のように細かく散って彼の顔を心地よく撫でた。彼の隣には、先程からケンと同じように、眼前に横たわる厚いガスに覆われたイギリス本土をじっと見つめている、背の高い男がデッキに立ちつくしているのにケンは気づいていた。
その男は、ケンと目が会うと、「ハーイ。」と少年のように笑った。
その男は、顔中髭に覆われていて、黙っていれば中世のバイキングを思わせる風貌をしていたが、笑った時に見せるあどけない表情が何ともアンバランスであった。
「僕は、ケンだ。よろしく……」
ケンは目で挨拶をしながら右手を差しだした。
「僕は、ケビン……。ケビン・トレーシー。」
ケビンは、そのグレーの瞳を大きく見開くと、差しだされた手をその大きな手で力を強く握りしめながら言った。
「君も一人旅なのか?」
「ああ……」とだけ、ケンは無造作に答えると、
「目的地は?」ケビンは、さも興味ありげに続けた。
「まだ決めてないが、とりあえず、ロンドンにしばらく滞在しようと思っているんだ。」
ケンは、シャツの襟を立てながら言った。
「君は?」
「僕は、イギリスを少し旅行した後、アイルランドへ行くんだ。」
ケビンは遠くを見つめるような目で答えた。
二人は、ドーバー港で汽車に乗り換え、一面、牧草に覆われたなだらかな丘陵地帯に放牧された牛や羊の群れを窓外に見ながら、2時間ほどでロンドンのビクトリア駅に着いた。駅はプラットホームも構内も旅行者でいっぱいだった。
二人は、人垣をかき分けながらプラットホームを抜け出し、旅行案内所前の長い列の中へ割り込んだ。行列の最後列は駅の構内からはみ出て、通りのはずれまで続いていた。
学校が休みに入る6月から9月までは、パリもロンドンも他の主だったヨーロッパの都市と同じようにバカンスを求めて移動する人々で溢れかえる。
イギリスは斜陽の国と言われて久しいが、ケンは、人々で埋まった光景を見て、それは間違いであると思った。少なくとも、こんなに多くの人々がイギリスへ集まってくる夏の間は、ポンドが上がっても不思議ではないと……。
「君たちは、B.B.(ベッド・アンド・ブレックファスト)を探しているのか?」
突然、後ろからコクニーアクセントが聞こえて来た。
二人が振り向くと、ケンたちよりは10㎝以上も背の高い、極端に痩せた男が、目玉だけをぎょろつかせながら立っていた。
「ああ、そうだが……」
ケビンが男に向かって答えた。
「そえなら、家は来ないか? 20ポンドでどうだ?」
男はケビンとケンを交互に見ながら言った。
「二人で20ポンド?」と今度はケンがたずねた。
「と、とんでもない。もちろん、一人ずつだよ……」
男は手を大きく振りながら、冗談じゃないと言わんばかりの顔をした。
二人は、目を見合わせて、考え込んでいる様子だった。
「分かった……。君たちには負けたよ。じゃあ、一人15ポンドにしよう。」
男は、二人を通常は、一人用のベッドの一つしかない部屋に押し込むことを思いついていた。
男は、自分の名前を「リチャード」だとだけぶっきらぼうに自己紹介すると、二人をヴィクトリア駅裏の路上に停めておいた古ぼけたトヨタカローラに押し込むと同時に、タイヤの音を軋ませて、すぐに車を走らせた。
今までヨーロッパで左ハンドルの車を見慣れていたせいか、日本と同じ右ハンドル仕様の車を見てケンは何となく、違和感を覚えたのと同時に、こんな大男が、今にも壊れそうなこんな古ぼけた小さな車を運転していることにやや不信感さえ感じた。
3人を乗せた車はテムズ河畔の脇道をうまく渋滞を避けながら、30分ほど走って、住宅街の中のこぢんまりした家の前で止まった。家の前には、優に30フィートはあると思われるヨットが家の大きさとは対照的にアンバランスな感じで置かれていた。
カローラを降りた二人は、リチャードに案内されて、小さな玄関を通って薄暗い家の中へ入った。ケンは、カビ臭い古びた匂いで少し気分が悪くなるのを覚えた。
二人が通された居間には、既に数人のアラビア系らしき客がいて、何やら、話に夢中であった。
「さあ、みんな紹介しよう。ケンとケビンだ。」リチャードの声で、
一様に顔中に髭を生やしたアラブ人たちは、みな同時にこちらに顔を向け、アラブ訛りの英語で、それぞれの名前を紹介した。
ケンとケビンはビクトリアステーションで立ち続けていたために、疲れ切っていてそんな難しいアラブ人の名前は、とても覚えるような気にはなれずに、“ハーイ”とだけ言ってその場を離れた。
リチャードも居間の先客に二人を紹介すると自分は、そそくさとキッチンの方へ消えていった。
二人は、あらかじめ教えられていた、2階の自分たちの部屋へ入って驚いた。
部屋は狭い上にベッドが一つしかないのである。
ケンとケビンは、顔を見合わせ、リチャードにしてやられたと思った。だが、一部屋という約束で借りたので今さら文句は言えないことは、二人には分かっていた。
二人は、ベッドのアンダーカバーを利用して床の上に、もう一つベッドを作ると交代でベッドを使うことにした。
ロンドンへ着いて3日目の朝だった。二人は毎日、ロンドンの街中を歩き回り、めぼしい所はほとんど行き尽くしていた。
その朝、ケビンはピカデリーサーカスが気に入ったから、もう一度行かないかとケンを誘ったが、ケンは毎日歩きずくめで、いささか疲れを覚えたために昼まで寝ていることにして誘いを断った。
ケビンが去ったあと、柔らかいベッドを一人で占領して心地よい眠りに再び陥った。
どれ程の間、眠っていたのだろう? 頬の辺りに何やら熱いものを感じた、うっすらと目を開けてみると、目の前にヒゲ面の男の顔があった。リチャードであった。
リチャードは、ケンが目を覚ましたのが分かると、自分の顔をケンの頬に押しつけて、さらにケンを抱擁しようとベッドの上に馬乗りになってケンの両手をその大きなごつごつした手で、
身動きが取れないように、鷲づかみした。
ケンは、ただごとではないと思い渾身の力を込めて逃げようとしたが、一回りも大きいリチャードの体は岩のように重くのしかかってきてびくともしなかった。
彼は、半分冗談めいて、かわいいだの、柔らかい頬をしているだのと言いながら、更にケンに口づけしようとヒゲに覆われたユダヤ人のような顔を近づけてきた。
リチャードの形相からして、悪ふざけではないことは、明らかだった。
ケンは、今度は思い切って、彼の股間を蹴り上げた。
これは覿面の効果があった。その大男はもんどりうって床へ転げ落ちた。その隙にケンは、部屋を飛び出すと裸足のまま表へ走り出た。
彼は、ウィンブルドンの駅まで歩いていき、そのままケビンが帰って来るまで待った。着の身着のままで飛び出して、金は一銭もなかったから、リチャードのいる家に戻る気には到底なれなかった。
夕方になって、ウィンブルドンの地下鉄の出口に現れたケビンは、ケンの姿を見るなり、腹を抱えて笑ったが、その理由を聞くともっと笑って、ケンが怒って一人で立ち去ろうとするのを見て、やっと笑うのを止めた。
「だって、ケン、そんな話、初めてだぜ……。あのおっさんにそんな趣味があったとはな。はっはっはっはっは……」
ケビンは、涙を流してまた笑った。
二人は、リチャードのB.B.を予定よりも3日も早く切り上げ、何の当てもなくウィンブルドンから地下鉄に乗り、ビクトリア駅へと向かった。
「ケン、君はソールズベリーへ行ったことはあるかい?」
とケビンがそのグレーの瞳を輝かせながら聞いた。
「いや、ないけど……。どうしてだい?そこに何か特別なものでもあるのかい?」
ケンは、興味はないとばかりに言った。
「大聖堂があるんだよ。ここは以前、ウェールズ地方の中心地だったんだ。もし、よかったら行ってみないか。」
「ああ……、そうだな。特に当てはないし、君が行ってみたければ付き合うよ。」
ケンは、あのような変わった経験をしたあとだったので、ロンドン以外であればどこでもよかった。
「それに、ソールズベリーには、ユースホステルもあるし、ホテルの心配をすることもないんだ。」
ロンドンから西北に250㎞ほど離れたウェールズ地方にソールズベリーは位置し、ロンドンからは蒸気機関車で3時間ほどの旅だった。ロンドンから比べると街は小さく、典型的な田園都市であった。道行く人々は、素朴で屈託なさそうに見えた。ケンは、いっぺんで、この小さな街が好きになった。
今まで旅をしてきた中で、一番自然の匂いの残っている街だった。
二人は、駅前のフィッシュアンドチップスの店で50シリング払って、新聞紙にくるまれた揚げたての魚のフライとポテトチップを買うと、歩きながら一気にそれを口の中に頬張った。
芳ばしい味が口の中全体に広がり、朝から何も食べていない空腹感も手伝って、今までに味わったことのないような高級な料理よりも比べものにならないほど、美味しく感じられた。
二人は、フィッシュアンドチップスを口いっぱいに頬張りながら重いリュックを背負って、とぼとぼと目指す大聖堂へと歩いていった。
大聖堂は、ケンが期待していたほど大きく壮麗なものではなかったが、処々、朽ちかけた石造りの柱や壁が歴史の重みを感じさせた。
ケビンが言うように、歴史的に重要で、有名な割には、ヨーロッパの各地で見たような華やかさが感じられないせいか、観光客の姿もほとんど目にしなかった。二人は大聖堂の裏に流れている小川に沿って、畑の中の小道を歩いていった。
小川の中では、鮒やら、鮠などの小魚がいっぱい、自由に泳ぎ回っていた。
途中、真夏だというのに革の手袋をした少女が自転車に乗って、白い息を吐きながら、ケンたちとすれ違った。
「まだ、夏だということをすっかり忘れそうになっちまうよ。」
ケンは、両手をジーンズのポケットに突っ込みながら、ケビンに話しかけた。
「そうだな。ヨーロッパの夏は涼しいけど、イギリスでは、特にそれを感じるよ。僕の故郷のミネソタは、今頃蒸し暑くて夜も眠れない位だというのに……」
ケビンは、なつかしそうな目をしながら言った。小川では、アヒルやら、白鳥が小魚と一緒に泳いでいた。ここでは、人間と自然が完全に調和していて、人も風景の一部に融け込んでいた。
「僕の育った神戸の街も、自然が多くて、僕は週末になると、決まって、家の裏にある六甲山へ家族で登ったもんだ。特にクリスマスの前になるとみんなで手分けして、暖炉で燃やす薪を集めに裏山へ登ったんだ。ここには、そんな自然が残っている
し、空気に張りがあるような気がするよ……」
とケンは、自分の生まれ育った六甲を思い起こしながら感慨深げに語った。
ケンとケビンは、1週間ほどソールズベリーのユースホステルへ滞在して、その田舎町を隅々までくまなく歩き回った。
「ケン、君との旅は楽しかった。僕はこれから祖父の故郷のアイルランドへ行くよ。機会があったら、また、会おう。」
と、幾分、寂しそうな目をしながら、ケンに別れを告げた。
ケンは、いつも別れは辛いものだと思いながら、ユースホステルの玄関に立って、いつまでもケビンの後ろ姿を見送った。
ケンは、ソールズベリーに更に一週間滞在した後、イギリスを後にした。
第5章「再会」へ続く
お問合せ
ご意見・ご感想などお聞かせください。