毎日、いつも決まったスケジュールで生活するのは、安全だから少しつまらないこともある。若い日の燃えるような情熱も、もう今では、その大部分は消え去ろうとしている。
数日前のことである。私は、思わぬ人から電話をもらった。
「アロー、ケン?、セ、シャルル……」
私は、一瞬、呆然として、しばらく受話器を持ったまま何も話すことができなかった。
その電話は、一瞬にして、20年以上も前に青春と共に捨て去った遠い記憶の真っ只中へ私を放り込んだ。
「大韓航空機(KE)ソウル行945便にお乗りの方は、ただいまより搭乗手続きを始めますので、3番ゲートよりご搭乗下さい。」
アナウンスが国際線のロビーに流れると、乗客は一斉に出発ゲートへと急ぎ始めた。
ケンは食べかけていたスパゲティーの残りを、急いで口の中へ放り込むと、水で一気に喉の奥へ流し込み、側に置いてあったリュックを右肩へ引っかけるや否や出国手続きカウンターへ向かうために、レストランのキャッシャーを足早に通り過ぎようとした。
「ありがとうございました。この次もお待ちしております。」
中年のマネージャーらしきその人物は、蝶ネクタイに黒のタキシード姿でケンに深々と頭を下げた。
ケンは反射的に
「どうもごちそうさま、また来ます。」
と若者らしく、ぴょこんと頭を下げただけでそのまま立ち去った。出国手続きを済ませ、懐かしいパリへ旅立つ期待感で胸はいっぱいだった。
ケンは、出発ゲートにまだ列をなしている一塊の人々の中に要領よく紛れ込むと、急いでゲートを抜け、息せき切ってシャトルバスへ乗り込んだ。と同時に、
「あっしまった!金を払うのを忘れてしまった。どうしよう」
と突然思い出した。
「あなたもソウルに行くの?」
アメリカアクセントの英語が聞こえる方を振り向くと、背の高いブロンドの娘がケンに微笑みかけてきた。
ケンはとっさに「僕に話しているの?」と聞くと、彼女は「他
に誰がいるの?」と言いながらケンの隣のつり革に長い腕を伸ばして他の乗客を押しのけながら、ケンと並んで話し始めた。
「私、ジェニー。ソウルまで行くんだけど、あなたもソウルまでなの?」
「いや、ソウルからパリ行きに乗り換えるんだ。」
ケンはやや怪訝そうにその女性の顔をちらりと見ると、そのまま前に向き直ってそっけなく答えた。ケンは見知らぬ人間と話をするのは、あまり得意ではなかった。
ジェニーは、それでも人なつっこさそうに、親しみを込めながらしゃべり続けた。
「まあ、よかった。私もパリまでなの。ソウルで長いこと待たされるからどうしようかと思ってたのよ。本当によかったわ。パリまで連れができたんですもの……」
「あなた名前は? 国籍はどこ?」
ジェニーは可愛く笑ってみせた。
ケンは、よくも見ず知らずの人間にこんなに次から次へと話が出来るものだと、半ばあきれ、また半ば感心しながら、渋々とジェニーのブルーの瞳を見返しながら答えた。
「ケン、ケン・ヨシダ。国籍は日本とドイツ。」
「へえ、ハーフなの。アメリカ人かと思ったわ。私、ジェニー・ピーターソン。アメリカ国籍だけど、私の母はベルギー人で、父はイギリス系のアメリカ人よ。あなたはお父さんがドイツなの?」
ジェニーは、ますます興味を示すかのように、ケンを好奇の目で見つめながらたずねた。
ケンはまだ質問が続くのかと、ほとんど腹が立ちそうになるのをやっと抑え、
「いや、父は日本人だ」
と父が日本人であることを誇りに思いながら、吐き捨てるように答えた。ところが思い直したように言った。
「ところで、君は連れは居ないのかい?」
ケンは、もし彼女に連れがいたら早速うまいとこ逃げ出そうと考えながらあたりを見廻したが、他は日本人の団体の観光客や日本での休暇を終えてソウルへ引き上げていくアメリカの軍人の姿だけで、それらしき人物は見当たらなかった。
ジェニーは、そんなケンの気持ちを見透かしたかのように
「残念でした。私一人よ。私、旅をするときはいつも一人なの。でも、もしあなたが私のことがうっとうしかったらいいのよ。私一人で何でもできるんだから……」
ちょっと自尊心を傷つけられて、豆鉄砲を食らった鳩のように、目を丸くしながら、ほっぺたを膨らませながら言った。
ケンは、ジェニーのそんな微妙な心の変化には全く無関心に
「でも、女性の一人旅はちょっと危ないかもしれないな。」
と一人言を言った。
「だったら、パリまで一緒に行ってくれる?」
とジェニーは、長いまつげ越しに、ブルーの瞳で、ケンを上目づかいに見つめながら聞いた。
「でも、たぶん飛行機の中では別になると思うよ。これだけの乗客がいるんだから……」
「それは平気よ。私があなたのとなりの乗客と代わってもらうか、あなたが私のとなりの人と代わってもらったらいいのよ。ノープロブレム!」
「そ、そうだな。それはいい考えかもしれない。でも、そんなに簡単にいくかなあ。」
「だいじょうぶよ、日本人はみんな親切だし、特にブロンドの女の娘にはやさしいんだから。」
ケンは、この女は何てうぬぼれが強いんだろうと、いささか興醒めした。
ケンの母親もこの娘に負けず劣らずブロンドの美人だったが、ケンが生まれて20年間、一度も母のそんな軽薄な言葉は聞いたことがなかった。
ケンの母親は、父親がドイツ人で母がスペイン人というちょっと変わった両親のもとに日本で生まれたが、ほとんどアメリカで教育を受けた。
国籍はドイツでも、考え方や習慣は全くアメリカ人であった。ケンは、父親ももちろん愛し尊敬していたが、母親に対してはもっと違った意味の愛情を抱いていた。
そのためか、この年になるまで、同年代や年下の女性に対してはほとんど興味を持ったことがなく、対象の女性が現れると、いつも母親と比較してしまうのを自分でも意識し始めていた。
「ジャンボジェットって、そばで見るとやっぱり大きいわね。私、飛行機って大好きよ。」
シャトルバスは、大韓航空のジャンボのライトブルーの胴体に取り付けられたタラップの横にピタリと止まった。大部分の乗客がバスを降りるまで、ケンはしばらくバスの窓から大きな翼にぶら下がっている4基のエンジンをじっと見つめていた。
「何してんのよ。早く行きましょうよ。」
ジェニーは飛行機に始めて乗る子供が親をせかすように、ケンの腕を引っぱりながらケンと一緒に外へ出た。福岡の空は梅雨がようやく明けたばかりなのに真っ青に澄み切って晴れ上がり、南に湧いた入道雲が夏の到来を告げていた。
「ああ、いい天気だ。僕はこんな空を見ていると何でも出来るような気がしてくるんだ。」
ケンは一人言を言いながら、最愛の恋人とのしばらくの別れを惜しむかのような感傷を覚えた。
「アンニョンハセヨー」
タラップを昇るとケンと同じ年頃のスチュワーデスが、二人に明るくあいさつして来た。
「ハーイ」
と二人は交互にスチューワーデス達にあいさつを返すと座席番号を探した。
ケンはアッパーデッキの窓際の席だった。アッパーデッキは総て禁煙席だった。
ケンが一安心してリュックの中から飛行機の中で読むために空港で買っておいた「戦争と平和」を取り出し、リュックを前部の座席の下に両足で押し込んでいるところへジェニーがニコニコしながらスチュワーデスを伴って、現れた。
「あなたの隣の方にお話があって来たのよ。」
とケンに目くばせをすると
「すみませんけど、私の席と代わっていただけませんか? 隣の人、私の友達なんです。」
何のためらいも見せずにストレートにたずね、一緒に来ていたスチュワーデスが通訳をすると、ケンの通路側に座っていた中年の日本人女性は、笑顔を見せながら
「いいですよ。若い人は若い人同志の方がいいに決まってますから」
と気軽にジェニーの頼みを受け入れてくれた。
「ドウモアリガトー」
とジェニーが拙い日本語で深々と頭を下げながら礼を言うのを見て、意外に礼儀正しいところもあるんだなとケンは内心快く思った。
ジェニーは肩に下げていたショルダーバッグを棚に乗せると、ケンの隣にちょこんと座った。
「意外と簡単だったワネ。私の言った通りうまくいったでしょう。私に不可能なことはないんだから!」
と長いブロンドの髪を右手でかき上げながら、濃いまゆを片方だけつり上げ、さも得意気に言った。
ケンは、彼女の強引さと自信過剰の態度にちょっと反感を覚えたが、所詮、自分とは関係のない世界の人間だと思い直して、窓の外をちらりと見やった後、ジェニーの目を正面から見据えるとゆっくりと話し出した。
「ジェニー、僕と君とが知り合ってからまだ10分しか経たないけど、もし君が僕と行動を共にしたいのなら二人の間にルールを作らなくっちゃ……」
ジェニーの反応を見ながら続けた。
「僕も、これまで世界中を旅行してきたけど、君みたいに積極的は女の子に会ったのは始めてなんだ。だから、ときどき君のスピードについて行けなくなることがある。僕もストレートな人間は好きだし、自分でもそうありたいと思っている。」
「オーケイ。そんなの簡単よ。私もあなたの考え方に賛成だわ。もし、これからお互い嫌なことがあったら直ぐにその場で話し合いましょう。」

とジェニーは、赤いマニキュアを塗った真っ白い手をケンに差し出し、ケンは「オーケイ」といいながらその手をギュッと握った。見かけはラフな女の子に見えてもその手は柔らかく、やはり10代の女の子の手だった。
「ソウルに着くのは、1時間後だから3時頃かな。それから金浦空港で5時間ほど待ち時間があるけど、ジェニー、その間君はどうする?」
「ケン、あなたの予定は? あなた次第よ。」
「僕は、ソウルには特に知り合いが居ないから、別に何も計画はないけど……」
「そうね。韓国って特に何もおもしろいところがあるわけでもないし。あたしもロビーであなたと時間を潰すわ。」
大韓航空(KE)のジャンボジェットは、メイン滑走路で離陸の許可を待っていた。急にエンジンの回転を速め、ゆっくりと滑り出したかと思うとぐんぐんスピードを上げ、機体を30°程傾け宙に浮いた。一瞬体がシートへ押しつけられ座席へ垂らした両下腿の自由が奪われるのを感じながら、窓から眼下を見下ろすとみるみるうちに博多の街は積木のように小さくなり、博多湾に浮かぶ志賀島も片手で掴めそうな気がした。志賀島に打ち寄せる玄界灘の荒波も白い線にしか見えなかった。
韓国までは、飛行機でたった1時間の距離なのに、何度訪れてもケンには遠い外国であった。外見はほとんど日本人と変わらないのに、どこか全く違う文化と雰囲気を持った国である。ケンは数回訪れた隣国に対して、そのような印象を持っていた。
「何を考えているの?」
ジェニーの声に、一瞬、ケンは驚いた様子で
「え?いや、ただいつ見ても日本の景色と外国の景色はどこか違うなって考えていたんだ。特に韓国なんか博多からだったら東京に行くより近い距離なのに全く違う風景なんだ。君も韓国へ行ったことあるの?」
「いや、初めてよ。パリには何度も行ったことがあるけどいつもアメリカから直接行ったから、ソウルを経由して行くのは全く初めてなの。」
飛行機は、既にソウルの上空へさしかかっていた。眼下には、茶褐色のビル群がびっしりと並んでいた。
恐らく、労働者のための団地が何かだろう。その向こうには、もくもくと煙を吐き続ける工場群と火力発電所が見え、最も日本の風景と際立つ点は緑が少ないことであった。
ジャンボジェットの小さな窓から見る光景は、茶褐色と灰色の
世界だった。その灰色の世界から続々と工業製品が生み出されて行く。韓国は小さいながらも第2の日本になるべく、着々と工業化を進めているニーズ諸国の中でも最有力国だ。日本が欧米の圧力に屈服し、市場開放だ、労働時間短縮だ、と血道をあげている中、着実に地歩を固めて来た。
「灰色の街はその発展の象徴なのかもしれない。」
などと思っている間にケンたちを乗せたジャンボジェットは、金浦空港に滑るように降り立った。
この空港は、軍との共用となっているため、様々な型の軍用機が所狭しと並んでいる。空港内の要所には、警備のための迷彩服を着た兵隊が銃を構えている。やはり、ここは日本から遠く離れた異国である。言葉も違えば、文化、風俗、習慣の全く違う。大陸文化と島国の文化との違いなのだろうか。タラップをジェニーと共に降りる。冷たい空気が鼻孔の奥まで浸み渡り、ケンの前頭葉を刺激した。
「空気まで違う。」
ジェニーも呼応するかのように「そういえば、顔立ちも日本人とは違うような気がするわ。」と言った。
ジェニーは初めての戒厳令下の国に、少しばかり緊張を隠しきれない様子である。
乗客はタラップを降りると、がっしりとした体つきの軍服に身を固め、マシーンガンを両手で構えた臨戦体制の軍人の見守る中を空港のロビーまで歩かされた。これも文化の違いかと多少不満を覚えながらロビーへ辿り着いた。
ロビーには国際空港らしく様々な人種の人々が、出発時刻までの時間を潰していた。ロビーの中には、レストラン、デューティーフリーショップなどが入っており、ケンとジェニーは、とりあえずしゃれた雰囲気のレストランに入って行った。
「ケン、あなたはここへはもう何度も来たことがあるの?」
ジェニーは、いま運ばれてきたばかりのレモンティーにシュガーを入れながら聞いた。
「そうだな、今度が4回目だと思うよ。一番最初は、僕が3歳のとき、母と祖母、それに妹のニコラと4人で来たのが初めてだ。その次は、中学の時に父がヨーロッパに行くのに一緒に連れて来てもらった。3度目は、カレッジに入った年に記念にヨーロッパまで、一人で、6ヵ月間旅行したんだ。だから、今度が4度目さ。KEが一番安いから、多少不便でもいつも利用してるんだ。」
「今度は、パリへ何しに行くの?」とジェニーは長いまつげ越しにケンを見つめながら優しくたずねた。
「ソルボンヌへ留学するんだ。しばらく向こうで医学を勉強しようと思っているんだ。」
「へぇ、あなた医者になるの?」
「いや、まだはっきり決めていないけど、父が医者だから医学には前から興味があったんだ。」
「でも、どうしてパリじゃなければいけないのよ。」
「そうだな…。カレッジはアメリカに行ったんだけど、カレッジのときの旅行で立ち寄ったパリが、いっぺんで好きになってね。その時からいつかきっとパリに戻って来ようと思ってたんだ。それに、たまたま留学試験に合格しちゃったんでね。」
「私もパリは好きよ。私は毎年行ってるの。母方の叔父が向こうでレストランをやっているの。だから私も夏休みになるといつも叔父の家で過ごすのよ。」
「君は、もうカレッジに行っているの?」
「ええ、そうよ。」
「どこの?」
「USCよ」
「へぇ、じゃあ、うちの母と一緒の大学だ。母は、USCからUCLAの大学院へ行ったんだ。」
「そう、偶然ね。両親はラスベガスに住んでいるんだけど、私はハイスクールのときから家を離れたの。」
「へぇ、どうして?」
「15才のとき、一枚の書類を偶然見てしまったのよ……」
彼女は、暫く間を置いて、ゆっくりと話し出した。
「実は、私、養子だったのよ……。生まれてすぐに今の両親に引き取られたのよ。15才になるまで全く気が付かなかったわ。」
「で、君には、兄弟、姉妹はいないの?」
「兄が一人いるの。でも、彼も養子なのよ。だから私、ショックで、両親を憎んで家を飛び出したの。」
「それで?」
「それから一人でアパートを借りて…、でも両親が全部面倒を見てくれてたんだけど……。今でも半分は両親に世話になってるわ。」
「で、今でもご両親のこと、そんな風に思ってるの?」
「いいえ、その反対よ。両親には感謝しているし、血は通っていなくても私にとっては最愛の人たちよ。勿論、兄も含めてね。」
「君のご両親は、きっと君と同じ位に君のことを愛していると僕も思うよ。血が通っていなくたって、家族なんだから。」
「ケンのご両親は今どこにいらっしゃるの?」
「今は、スイスのローザンヌに居るんだ。父がローザンヌのボードワ大学の教授をやっているんだ。でもいつも世界中を飛び廻っているよ。」
「あなたたち、アメリカ人? 一緒になってもいい?」
突然ケンの後ろで女性の声が聞こえた。
振り向くと、ジーンズにタンクトップ、栗色の長い美しい髪を背中まで垂らした若い白人の女性が立っていた。
「勿論さ、さぁ、どうぞ」
ケンは立ち上がって、その女性にイスを勧めた。
「私、ケイト、よろしく。」
その女性は、座る前に二人に軽く挨拶した。
「僕はケン、こちらはジェニー、僕たちパリ行きの便を待ってるんだ。君は?」
「私もよ。」
長い栗色の髪を両手で後ろにかき上げながら、ケイトはそのブルーの瞳を輝かせながら言った。
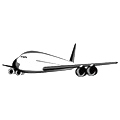 第2章「出会い」へ続く
第2章「出会い」へ続く
お問合せ
ご意見・ご感想などお聞かせください。
