パリの街は、まだ長い夏が続いていた。ケンの毎日は、あの事があってからもいつもと同じように過ぎていた。
他のフランスの学生とは違って言葉にハンディのあるケンには、他の学生と同じように夏のバカンスを楽しむ余裕はなかった。
毎日、朝から夏期講座へ出て、午後からはマリーの子ピエールのベビーシッターの仕事が待っている。週末は、ローザンヌでの水汲みとパリのカフェでのアルバイトで忙しかった。彼は、むしろ忙しい方が有難かった。
彼は、自分に貧乏な境遇を与えてくれた神様に感謝した。週末のローザンヌのマクドナルドの店でリサと会うのも今の彼には救いであった。だが、改善の兆しは見られなかった。
「ケニー、この頃どうしたの? いつもと違って何か変よ。」
リサは、女性特有の直感で、ケンの心の中に起こった異変に気付いていたが、それ以上は別に聞こうとはせずに、彼が来る度にいつも笑顔で迎えてくれた。ケンには、リサのこの底抜けな笑顔と明るさが嬉しかった。
ある週末の夕方、ケンがローザンヌからドームの自分の部屋へ戻ってみると、部屋の前にシャルルとケイトが立っていた。
「やあ、シャルル……。ケイト! どうして、君たちがこんな所に二人揃って居るんだ?」
ケンは、この偶然に驚きながらたずねた。
「今朝、一度あなたを訪ねて来たら、他の部屋の人が、土曜日はいつも夕方帰って来るって教えてくれたの。だから30分程前に来てみたら、あなたのお友達のシャルルも来ていて、偶然ここで会ったのよ。二人であなたの事を色々と話してたら、あっという間に時間が経ったわ。」
ケイトは、いつもと違って、薄いピンクのワンピースにハイヒールを履いていて、一層背が高く、ヴォーグの雑誌から抜け出して来たように美しく見えた。
「ケン、こないだから何度訪ねて来たって居ないから、僕もミッシェルも随分心配していたんだぜ……。だから、今日こそは逃すまいと思って、ずっとここで待ってたんだ。今日は、カフェのアルバイトもない日だろう? 今晩は、一緒に食事にでも行こうじゃないか。ミッシェルも、部屋で待ってるんだ。ケイトも、今日は予定がないっていうし、ダブルデートといこうよ。」
シャルルはケンの心中を察してか、ケンを励ますために一生懸命だった。
「ねぇ、ケン、いいでしょう。こないだ、シャンゼリゼで会って以来、パリに出て来て一度もあなたとデートした事ないのよ! 今晩くらい、いいでしょう?」
ケイトは、強引で、一歩も譲る気配は見せなかった。いつもとは、やはり少し様子が違って見えた。
「OK!」ケンは、彼らがこれ程までに言うのなら仕方がないと諦めた。
彼ら3人は、サンミッシェルで、シャルルの恋人ミッシェルと落ち合い、そのままシャルルの案内でカルチェラタンにある彼の馴染みのフランスレストランへ行った。
古い煉瓦造りで、表面を蔦で覆われた、その店は300年近い歴史を持つ老舗であり、数多くの歴史上の人物が訪れたことがあるとシャルルは説明してくれた。
中へ入ってみると壁は一面汚れていて、その薄汚れた染みの一つ一つが歴史を感じさせるとケンは思った。
四人は、洞穴のようになった一番奥まった場所のテーブルに案内された。テーブルの上には古い燭台が一つ置いてあり、蝋燭の炎が辺りを薄明るく照らしていた。
四人がテーブルに落ちついたのを見はからったかのように、やがて金髪の少し禿げ上がった背の低い中年のウェイターが恭しく注文を取りに現れ、一人一人にメニューを渡しながら、本日のお勧めメニューを早口で説明し始めた。
シャルルは彼の説明が終わるのを待って、みんなにワインの希望をたずねた。とりあえず、白のドライで銘柄はウェイターに任せることで意見が一致した。
ウェイターは、一旦、ワインを取りに戻ると、再びワインを持って現れ、コルクをシャルルに渡した。彼は、それを鼻先でちょっと臭いを嗅ぐ仕草をし、ウェイターが注いでくれたワインを舌先と喉で味を確かめ後「ウィ」と短くウェイターに言った。
「皆の健康を願って、乾杯!」
四人は、それぞれウェイターが注いだグラスを高く掲げると一気に中身を飲み干した。舌ざわりのいいまろやかな、しかし、刺激的な液体が喉を通って食道から胃まで落ちて行くのがケンにはよく分かった。これが生きている証だと彼は思った。
空きっ腹に染み渡るアルコールは、胃の粘膜を刺激すると同時に速やかに粘膜下の毛細血管から吸収され、肝臓を素通りして心臓まで運ばれ、そのまま動脈を通って、脳細胞へと到達した。数分間で完全に大脳まで運ばれたアルコールは、大脳辺縁系を麻痺させ、人間としての常識の抑制を取り除いてします。

ケンは、今までアルコールは余り口にしたことがなく、決して強い方ではなかった。
しかし、今日の酒は幾らでも飲めるような気がした。
「ケン、今日は最近めずらしく上機嫌みたいね。」
シャルルの恋人、ミッシェルが打って変わったような陽気なケンを見て、驚きながら言った。
「うん、今日は久し振りにみんなに会ったんで嬉しいんだよ。特に、わざわざケイトも来てくれたし……」
ケンは、今は本当にそう思っていた。わざわざ、自分の事を思って訪ねて来てくれた美しいケイトに感謝していたし、同時に何かいつもとは違った魅力を感じていた。
「ケン、そう言ってくれると私も嬉しいわ……」
ケイトは、うっとりとした目で、ケンを見つめると右手で彼の手をぎゅっと握りながら言った。ケンは、敢えてその手を振り解こうとはしなかった。
やがて、先程の中年のウェイターが、メインディッシュを運んで来た。
「さあ、みんな今日は僕の奢りだ。遠慮なく食べてくれ……」
シャルルはそう言うと、皆にもう一度ワイングラスを高く掲げてみせた。その日の食事は、ケンにとっては思いがけないご馳走であったのと同時に、友情の尊さをしみじみと感じさせてくれた。四人は心ゆくまで食事とワインを楽しんだ後、セーヌの河畔を散歩した。
シャルルとミッシェル、ケンとケイトはそれぞれ手をつないで、散歩しながら会話を楽しんだ。しばらく、散歩を楽しんだ後、
「ディスコへ行きましょうよ。」とケイトが言い出した。
誰も反対するものはいなかった。
ケイトの案内で四人が行ったディスコは、やはりカルチェラタンの中にある一見アメリカのディスコを思わせる近代的な建物の地下にあった。
四人が階段を降りていくと、タキシードを着た背の高い黒人の男が木製のぶ厚い扉を開け、中へ案内してくれた。
ドアを開けた途端にアメリカのロックミュージックが鼓膜を振動させ、脳底部まで揺れるような錯覚に陥った。
ケンにとっては、久し振りの衝撃だった。
もともとアメリカに居たときから、余りディスコのような人の集まる場所には興味がなく、滅多に訪れる機会もなかったのだが、たまにはカレッジの友達とビバリーヒルズやニューポートビーチのディスコへ行くことはあった。
「ここは、最高にイカすぜ。」
シャルルが、ケイトの耳元でフランス訛りの英語で叫んでいるのが聞こえた。
「ここには、よく来るのかい?」
今度はケンが、ケイトの反対側の耳に向かって叫んだ。
「ええ、ここはパリで私が一番好きなディスコよ!」
ケイトが思いっきり大きな声で答えた。
「あそこへ座りましょう!」
ミッシェルが、黒人のウェイターが指し示す座席にシャルルの手を引いて行った。
ケンとケイトも彼らの後に従った。
「ドン・ペリニヨン!」
シャルルは、黒人のウェイターに大きな声で言って、シャンパングラスを4つ持って来させた。
先ずケンが、シャルルとミッシェルの婚約を祝い、次いでシャルルが、ケンとケイトの再会を記念して乾杯を行った。
それから四人は、ロックの音楽に合わせて狂ったように激しいリズムで踊った。いつしか音楽は激しいロックから、メローなブルースへと変わっていった。
2組のカップルは、自然と抱き合い、音楽に合わせて踊り始めていた。
ケンは、その夜、生まれて初めて酒に酔った。恐らく、それまでジェニーの事で鬱積していた気持ちが、シャルルとケイトの温かい思いやりで一度に解けたためかもしれなかった。いくら飲んでも舌触りのいいシャンペンは、酔いを感じなかった。
シャルルは嬉しかった。こんなに楽しそうにしているケンを見たのは、久し振りだった。
最近は、急に塞ぎ込んでしまって一番親しい自分に何も話してくれないし、会おうとさえしなかった彼が、今晩は別人のように朗らかで、シャルルが一番最初に会った時のケンに戻っていた。ケイトも幸せだった。
これまでパリに来て以来、何度かケンに会おうとしたが、なかなか果たせなかった。でも、今夜はこうして自分のすぐ隣に、手の届く所に、好きな人がいる。それだけで充分幸せだと思った。
ただこうして、ケンの手を握っているだけでいい……。
ケンはかなり酔っていて、ミッシェルとケイトの顔の見分けもつかなくなっていた。
時々、妄想なのか、現実なのか、ケイトの顔がジェニーに見えたりもした。
ひょっとしたら、ケイトが気を利かしてケンのためにジェニー
を呼んでくれたのかもしれない。ケンは心の中で『ジェニー、ジェニー』と何度も叫んだ。ダンスフロアからは ♪リング、マイ、ベール、リング、マイ、ベール……リング、マイ、ベール♪ 有名な黒人の歌手の流行歌が聞こえてきた。
『頭が、ガンガンして締めつけられるように痛い。眩しくて目が開けられない。ここは何処だろう……?』
ケンはまだ夢を見ているのかと思った。シャンペンを飲んで、みんなと踊ったことまでは覚えているが、それからの記憶は全くなかった。思い切って目を恐る恐る少しずつ開けてみると、まぶしい夏の太陽の光が見覚えのあるレースのカーテン越しに部屋の中に差し込んで来ていた。
『多分、もう昼過ぎだろう……頭が割れそうに痛い! でも、何とか起きなければ……』と思いながら、鉛のように重い体を動かそうとした彼は、突然、温かいぬくもりを持った物体が、自分の体に触れるのを感じて飛び上がるほど驚いた。寝惚け眼を手で擦りながら目を大きく見開いてみると、何と自分の隣に下着姿のケイトが寝ていた。ケンが、信じられないといった顔でしばらくケイトを見つめていると、ケイトはようやく目覚めたらしく、まだ眠たげな声で
「おはよう……。よく寝れた?」
と聞いた。
「あ、ああ……」
ケンは曖昧な返事をしながら、
「で、でも……、どうして君がここに?」
やはり狼狽の色は隠せない様子だった。
「あら、昨夜のこと何も覚えてないの?」
ケイトは驚いたような顔をしながら、その大きな瞳でケンを見つめた。
「ああ、ディスコに行ったことまでは覚えてるけど……」
ケンは、その後のことを思いだそうと一生懸命に努力したが、無駄だった。
「あの後、あなたは動けなくなるほど、すごく酔っぱらってしまって、私たち3人でここまで運んできたのよ。」
ケイトは、ちょっと間を置いた後、
「ケン、まじめな事だけど……、あなた本当に、その後のこと覚えてないの?」
ケイトは、真剣な眼差しでじっとケンを見つめた。
「その後って?」
ケンは、ケイトが何を言っているのか、よく理解できなかった。
「え? 本当にあなた覚えてないの?……」
ケイトは、本当の事を言おうか迷いながら、どこか躊躇しているように見えたが、
「あなたと私があれだけ愛し合ったことよ……」
ケンを少しからかって、彼の反応を試すつもりで思い切って言ってみた。
ケンは、ケイトの言った事が何を意味するのか、まだ理解できなかった。というより、むしろ理解したくなかったと言った方がよかったかもしれない。彼は、ただ茫然として、しばらくケイトの顔を無意味に眺めているだけだった。
しかし、ケイトの真剣な顔を見ているうちに、ケイトの言葉が真実みを帯び、現実の物となってケンに重く覆い被さって来るのを感じた。
『酒の悪戯なのだろうか? とはいっても、取り返しのつかないことをしてしまった! 本当に愛していない女性とこんなことになるなんて……』
ケンは、ケイトに対する責任の重さに気づくと同時に、ジェニーに対して未だに僅かながら抱いていた希望の灯火が、一度に消えていくのを感じた。
『しばらく、パリを離れよう……』
ケンは心の中で、そう決心した。
翌日、ケンはいつものように、ピエールを迎えに幼稚園に行き、アパートでマリーが帰って来るのを待った。
定刻通り、マリーはドアのベルを鳴らした。ケンがドアを開けると、マリーはいつものように顔を満面にたたえて立っていた。
「サバ? ケン!」
マリーは、挨拶しながらケンの頬にキッスした後、ピエールの部屋へいつものように入って行った。
「サバビヤン!」
ケンは、愛想笑いをしながら答えた。心の中では、ちっとも元気ではなかった。ドアを閉めるとリビングルームへ戻った。彼は、窓際に立って、まだ明るい通りを眺めながら昨日のことを考えていた。
「ああ……メルシー」
ケンは上の空で答えた。
マリーは、キッチンから2組のコーヒーカップを手に持って現れ、その一つをケンに手渡しながら、自分はソファーに座った。ケンの物憂い態度を見て、
「どうかしたの? ケン!」
少し心配そうな顔でたずねた。
ケンは、手渡されたコーヒーカップを右手に持ったまま、マリーの向かいのソファーに座って、マリーの顔を正面からじっと見据えた。
美しい目だと思った。
「マリー、実は今日は君に話さなきゃならない事があるんだ……」
「えっ? なあーに?」
マリーは、不安そうに眉間に少し皺を寄せながらたずねた。
「実は、僕……、パリを離れなくっちゃならなくなったんだ……」
「えっ? でも、どうして?」
マリーは、ちょっと体を強張らせながらたずねた。
「今は、理由は言えないんだけど……、でも、どうしても離れなくっちゃならないんだ。それで、悪いんだけどピエールの事、もう面倒見れなくなると思うんだ。」
「ピエールのことなら、何とかなると思うけど、でも、どうして、そんなに急にいなくなるの?!」
マリーは、半ば、興奮しているのが、怒っているようにも見えた。
「悪いけど、それだけは今は言えないんだ……。僕も、大好きなパリと君やピエールと別れるのは辛い……。
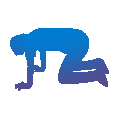
でも、今は、そうしなきゃならないんだ。」
「許してくれるかい?」
ケンは、マリーの美しい瞳をじっとみつめながら言った。
マリーは、ケンの固い決意を汲み取ったのか、しばらく黙っていたが、
「分かったワ」
とケンの目をじっと見つめたまま
「でも……、きっと帰って来てくれるわね。」
半ば自分に言いきかせるように、ケンの手を自分の両手の中にしっかりと握りしめながら言った。
「ああ……」
とケンは短く答えた。
「それじゃあ今日はあなたのために、とびっきりの美味しいご馳走を作るワ。今日は、遅くまで私に付き合うのよ。いいワネ!」
マリーは、今までの沈んだ態度とは打って変わって、急に元気を取り戻したように、振る舞った。
ケンはその夜、マリーの言う通り二人で最後の食事をした後、マリーのアパートに泊まった。
リビングルームにマリーが用意してくれたソファーベッドの上でまるで天使のように安らかに眠った。
マリーは、夜中にぐっすり眠っているケンの側にそっと忍び寄って行くと、しばらくの間、その清らかな寝顔を見つめていた。
”このままケンを自分のそばに永遠に置いておきたい!” と思った。
第4章「傷心の旅」へ続く
お問合せ
ご意見・ご感想などお聞かせください。

